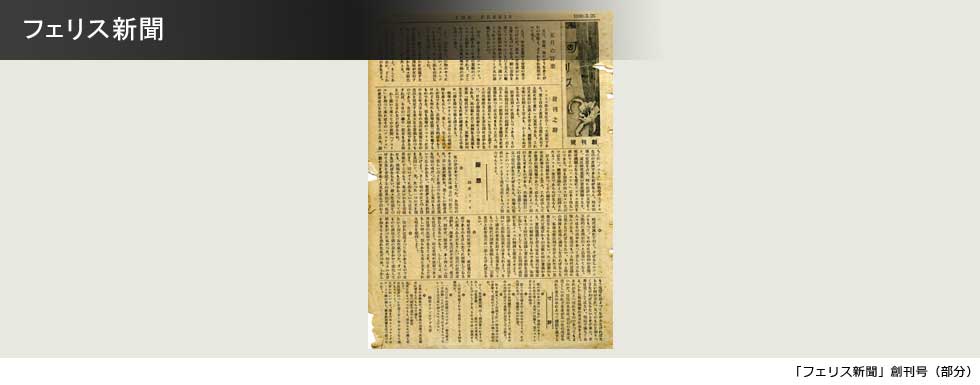「フェリス新聞」は1930年5月25日、学友会(現在の生徒会に近い組織)の編集部によって『フヱリス(THEFERRIS)』として発刊された。アメリカの大学新聞のように生徒自ら編集・発行を手がける方式で、日本で最も古い学生新聞の一つとされている。創刊号の「発刊之辞」には次のように書かれている。
「フヱリス」は我等のフヱリス生活の反映であらねばならん。時に指導の位置を占め、時に批評の立場をとり、或は研究思索の発表機関となり、報導機関となるも常にフヱリス生活を離れてこの「フヱリス」はあり得ないのである。
『フヱリス』は当初月刊として発行されていたが、1941年に校名が変更され、学友会が報国団に変わったことにより横浜山手女学院報国団発行となった。その後、戦況の悪化や物資の不足などにより1943年11月22日発行の104号をもって休刊。
戦後もしばらくは物資の不足などにより新聞を発行することはできなかったが、学友会に「新聞部」が発足し、1948年7月、105号から復刊した。105号の巻頭には「復刊の喜び」と題して次のように記されている。
本年度の学友会に新聞部が生れ、新しく活動を始めたことは心から喜びに堪えない。(中略)
今や学園復興の機運も熟し、今後の発展も大いに期待される折柄、この伝統あるフヱリスの発展の一駒一駒を記録する新聞部の役目も決して忽に出来ぬ責任がある事を思うのである。部長部員の懸命なる努力を期待してやまない。
「フェリス新聞」は生徒の視点から学校生活を伝え、その時代に合わせた特集や取材を行い在校生に報じてきた。現在もフェリス女学院中学校・高等学校新聞部により『Ferris』として発行され、2025年3月の時点で336号を数えている。
歴史資料館では『フェリス新聞』のほか、短期大学学生新聞『Ferris Junior College』(1961年頃創刊、1969年12月18日号まで確認)や、大学学生新聞『Ferris Gazette』(1966年6月創刊、1976年7月8日号まで確認)も所蔵している。それぞれ欠号があるので、お持ちの方はぜひご連絡いただきたい。
(歴史資料館)