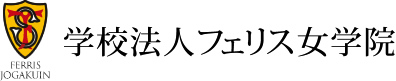
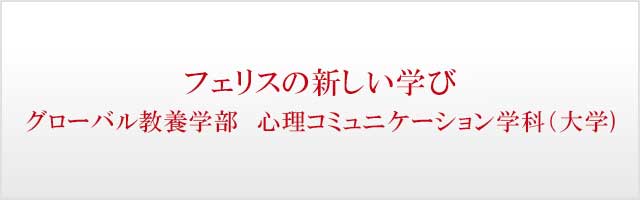
フェリス女学院大学では学部・学科の発展改組を行い、2025年度からは新たに1学部3学科9専攻体制となります。
今回、「国際社会学科」「文化表現学科」とあわせて開設した「心理コミュニケーション学科」の学びの特色について、学科主任の小ヶ谷千穂教授にお聞きしました。
心理・メディア・共生を組み合わせ、実践的に学ぶ
近年は、社会における多様性が注目されるようになっています。ジェンダーやセクシュアリティの多様性への関心も高まっていると言えるでしょう。一方、生きにくさを感じている人、困難を抱えている人も少なくなく、理想である「誰もが生きやすい多様性に満ちた多文化共生社会」の実現は容易ではありません。この課題に実践的にアプローチするべく設置されたのが、心理コミュニケーション学科です。
心理コミュニケーション学科は、「心理専攻」「メディア専攻」「共生コミュニケーター専攻」の3つの専攻からなります。既存の文学部コミュニケーション学科での学びを引き継ぎつつ、心理・メディア・共生の3つを組み合わせながら幅広く学んでいくのが特徴です。
心理コミュニケーション学科では、多文化共生社会をいかに実現するかに主眼を置いており、実際に地域に出て活動するフィールドワークを重視しています。例えば、日本語以外を母語とする人のサポートというのは、ニーズがあるのにそれを担える人が少ない分野です。授業では、外国にルーツをもつ子どもの学習支援に携わることなどを通して、当事者の心に寄り添い、当事者目線でリアルな課題を体感する機会を設けています。
また、教員に地域社会で活動する実践者や実務経験者が多いのも特徴です。座学で知識や理論を学ぶだけでなく、実践を通してアクティブに学び、調査法、データの分析法、取材の手法、表現法、語学力といった「スキル」を習得することも大切にしています。
多文化共生社会のスペシャリストを育てる
他の2学科と同様、心理コミュニケーション学科でも、1・2年次は心理・メディア・共生を柱に幅広いテーマについて学んでいきます。さまざまなテーマや視点に触れるなかで自分の興味・関心を見いだし、3年次からは3つの専攻に分かれます。
心理専攻では、「人の心」のやりとりを理解・支援するための心理学的な知識やスキルを身につけていきます。メディア専攻では、「人の心」を伝えるための手段としてのメディアについて、その表現方法を含めて学んでいきます。そして、共生コミュニケーター専攻では、外国にルーツをもつ人の抱える困難や性の多様性といった視点から、共生社会を実現するための方法を地域社会でのフィールドワークを通して学んでいきます。
共生社会の実現のためには、困難を抱えている人に対する心理的な支援や生活支援を含めた包括的なサポートが不可欠です。地域で、企業で、学校で、多様性への理解や配慮が求められるなか、こうしたことを専門的に学んだ人材へのニーズは今後ますます高まるでしょう。その意味においても、多文化共生社会のスペシャリストを育てる心理コミュニケーション学科の存在は、まさに時代の要請に合ったものだと思います。
社会人にも門戸を開き多様で豊かな学びの場へ
心理コミュニケーション学科での学びは、既存の学問の枠に収まらないところにそのおもしろさがあると感じています。多様な視点、多角的なアプローチが可能で、学生の自由で新しい発想から、私たちが思いもよらないような交差やミックスが生まれることもあるでしょう。良い意味で変化していく学科でありたいので、その柔軟性や流動性を促せるような環境や気風をつくっていきたいと思います。
そして、社会に出られた方々のリスキリングや学びの場としても、心理コミュニケーション学科はニーズが高いのではないかと考えています。社会における不平等や多文化共生社会の実現に向けた課題を実際に経験された方々が若い学生と共に学び合うことで、まさに多様性が生まれ、学びがより豊かになることでしょう。社会人入学のほか科目履修という選択肢もあります。卒業生や保護者の方々のご入学・ご受講もお待ちしております。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
心理コミュニケーション学科の学びとは?
多様性や共生の理想を実践する視点を学ぶ
心理コミュニケーション学科では、人の心やコミュニケーションの多様な形を学び、他者との関わりを深める力を育てます。 心理学、メディア、社会学などを学び、多文化共生を支えるスキルを身につけます。また、実践を重視したカリキュラムにより、 心理的サポートや効果的なコミュニケーション方法を探究し、地域や国際社会での調整役として貢献できる人材をめざします。

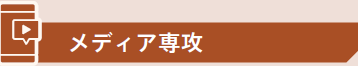
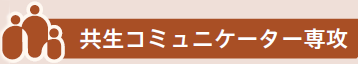


| 認定心理士 | 公認心理師 [学部単位の取得] | 社会調査士 | 日本語教員養成 講座修了証 | |
| 心理専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メディア専攻 | ― | ― | 〇 | 〇 |
| 共生コミュニケーター専攻 | ― | ― | 〇 | 〇 |


小ヶ谷千穂 Chiho OGAYA
心理コミュニケーション学科主任
一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。日本学術振興会特別研究員、横浜国立大学准教授を経て、現在本学教授。専門は国際社会学、ジェンダーと国際移動。
フィリピン人移住者とその子どもの研究に携わる。現在、川崎市多文化共生社会推進協議会会長、横浜市男女共同参画審議会会長。

心理専攻
学校臨床心理学ゼミ
学校現場で生じる子どもたちの適応の問題、対人関係の課題、学齢期の子どもたちが抱える精神健康の問題に対して臨床心理学ができる支援方法について学び、考えます。

メディア専攻
ケアメディアゼミ
さまざまな分野におけるコミュニケーション不全の状況を、メディアを活用し正常にするケアメディア活動がテーマ。理解から実践までの過程を学びます。

共生コミュニケーター専攻
多文化共生・国際社会学ゼミ
ジェンダー、セクシュアリティ、階級、人種などを題材に、学生同士での議論を重ねていきます。多文化共生の現場でのフィールドワークを通して国際社会学の基礎を学びます。
▶学生メッセージ
2025年度から始まった「心理コミュニケーション学科」の前身となる「文学部コミュニケーション学科」で4年間を過ごした先輩に、大学や学科の雰囲気、将来について伺いました。
Y.Uさん(4年)
知的好奇心と探究心が育まれる
専門分野を超えた多様な学びの場
専門分野を超えて私の「知りたい」を探究できる学びの環境
キリスト教という学問に加えて、身体表現、いわゆるノンバーバルコミュニケーションについても学びたいと考えてフェリスを選びました。講義形式やグループディスカッションなど多様なスタイルの授業があり、自分の専門分野以外も学べたり、作品制作やワークショップに参加したりと、さまざまなことを学べる環境です。また、少人数で学べるため、先生との距離が近いことも魅力です。
キリスト教への関心とゼミの学びを元にした卒論テーマに取り組む
卒業論文は、キリスト教とゼミで学んでいる「作品構造分析」を活かせるようなかたちで、取り組んでいきたいと考えています。将来は中高の宗教の教員免許を取得し、母校で働くことも視野に入れています。「誰かのためになにかをしたい」という「For Others」の精神を形にし、社会に貢献したいと思っています。